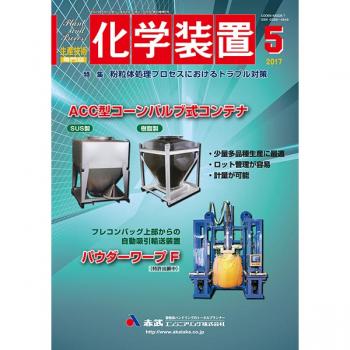化学装置 2017年5月号
【特 集】粉体処理プロセスにおけるトラブル対策
- 粉体処理プロセスにおけるトラブル・エスケープルートの考え方
- 吉原伊知郎技術士事務所 吉原 伊知郎
- 粉粒体の乾燥操作の基本事項と一般的なトラブルと対策例
- 静岡大学 立元 雄治
- 粉体プラントにおける粉塵爆発とその危険性および爆発対策
- 日本フェンオール 舛本 慎太郎
- 粉粒体の空気輸送システムにおける付着防止
- 赤武エンジニアリング 鈴木 政和
- 粉粒体の混合操作におけるトラブル対策
- 徳寿工作所 朝日 正三
- 高低差のある粉体搬送のトラブル対策
- ワイ・エム・エス 荒井 竹志
- 噴霧乾燥・造粒操作におけるトラブル対策
- 大川原化工機 河合 研一
- 低融点樹脂粉砕の現状と対策
- 日本コークス工業 関根 靖由
【隔月連載】
- グローバル時代の化学企業のリスク管理(1)
- 化学工学会SCE・Net安全研究会 澤 寛
【一本記事】
- 高機能シートおよびプリプレグ(複合材料)〔下〕
- 東京医科歯科大学 宮入 裕夫
【短期連載】
- 究極の重質油分解装置 Ⅱ.日本の石油精製の課題と対応
- 化学工学会SCE・Netエネルギー研究会 原 晋一
□巻頭言□
- 産業発展の基盤を築く粉体工学
- 大阪大学 内藤 牧男
○技術トピックス○
- 品質コントロールの自動化が図れるインプロセス・リアルタイム粒子計測システム
- SOPAT GmbH
【連 載】
- 粉体の計量とその制度の実践的解説(5)
- フルード工業 小波 盛佳
- プラントエンジニアリング・メモ(115)
- エプシロン 南 一郎
- 安全談話室(128)
- 化学工学会SCE・Net安全研究会
- 創造革新化・イメージマッピングによる「モノづくり」(11)
- 露木生産技術研究所 露木 崇夫
- 技術者のための創造力開発講座(34)
- 飯田教育総合研究所 飯田 清人
- 地球環境とバイオリアクター(30)
- 近畿大学 鈴木 高広
情報ファイル/ミニ情報/ 図書紹介/コラム/次号予告等。
【2017年5月号の見どころ】
5月号特集分:粉粒体処理プロセスにおけるトラブル対策での「粉粒体処理プロセスにおける『トラブル・エスケープルート』の考え方」(吉原伊知郎氏)では、次のような解説が成されている。
まず、“1,はじめに”では、「粉や粒を扱うプロセスでは、取り扱う原料が同じ化学式・組成でも、粒度分布・表面の活性・雰囲気の違いでその挙動は大きく異なる。起こりうるすべてのトラブルの可能性を想定し、あらかじめ対策を組みこむトラブル予防方法は、多大なコストがかかり、装置/システム全体の『コスト対パフォーマンス』は低下する。そこで、トラブル発生確率が低い事象には、万一発生した際に現場で直ちに対応できる仕組みをあらかじめ仕組んでおくものの、初めから施工はしないという『エスケープルートの考え方』が採用されている。この考え方は、条件さえ整えば誰しも使うことを望まない山登りのエスケープルートに似ている。山登りでは、天候の急変、隊員の体調不良、現地のルートの状況如何で、必ずしも予定していたルートを通れないことがある。その際は素早く事前に検討していたエスケープルートを使って危険を回避し、隊員を安全に平地に降ろすことがリーダーの務めである。筆者の山登りの経験と、粉体を扱うプラントのトラブル対応経験から、実際に実践してきた例を挙げて解説する」と。
また、“2,最近の粉体処理プロセスの動向”では、「粉や粒をその粒径で区別しようとしていた時代は、もはや過去の時代となり、重力や慣性力に支配される粒子と、付着力や表面の物性に支配される粒子の違いを理解して、粉体処理プラントを設計した方が合理的である。その意味で、“粉砕、乾燥、造粒及び表面改質、複合粒子、粒子接合”などは、“機能性粒子”を生産するために用いられる単位操作であるとも言える。」「造粒の範疇でも『目的とした場で分散し機能を発揮する為に軽く造粒したい』」という要望や、『一次粒子ではハンドリングできないために、粒子が機能する場に到達させるためだけに顆粒にしたい」という要望が近年増加している。』」と指摘している。
さらにまた「粉砕の範疇では、細かくすることばかりが粉体を利用する利点ではなく、界面で割る粉砕、エネルギーを蓄えること、表面で機械的に反応を起こすことなどが試みられ、熱を利用する分野でも、乾燥過程の制御で中空粒子を造ったり、反応と乾燥を同時に行う熱と物質の同時移動をするなど、新しい材料の要求とそれに対応する粉体に関する技術の進歩はめざましい」と強調。
「一方、国内に建築される新しいプラントの数はこの10年で大幅に減少しているために、本来、実務を経験し、試行錯誤を繰り返し、人間関係の煩わしさも含めて得ることのできる粉体技術者の勘所は、従前と比べて容易に体験・体得することはできなくなった。トラブルを体験し、予測できるエンジニアが自らの責任で対策を予め立てておくという安全対策は実行が困難となっている。プラントの安全は数値で表すことができるとされているが、安心は人間の感情なので数値化はできない。安全と安心は区別して議論することを念頭に奥と共に、粉体プラントに対応するトラブル解決方法には、それなりの覚悟と手法が必要である」と。
以下、吉原氏は、“工業用の機能性微粒子(【事例】コピーのトナー電池の正極・負極材、ITを支える 電子部品、医薬品)“、“なぜ粉体トラブルの予測が難しいのか(粉・粒の多様性、トラブルの分類)”“エスケープルートの具体例”等の解説を続けている。詳細は本誌をご参照ください。
※ 定期購読お申し込み後の購読契約は自動継続となります。
※ 海外からのご注文は別途、為替手数料がかかります。
FAX送信にてお申し込みをされる方はこちらのPDFファイルを印刷してご利用ください。
※Adobeアクロバットリーダーがインストールされている必要があります。
※クレジット決済ご希望の方は
こちら(富士山マガジンサービス)よりお申込み下さい。
(但し、国内ご契約のみとなります。)
1部:1,848円 (税込)※別途送料200円
定期購読一年:22,176円 (税・送料込み)
| ITEM NAME | 化学装置 2017年5月号 |
|---|---|
| ITEM CODE | PAP201705-f~PAP201705-m |
| PRICE | 1,848~22,176 円(税込) |