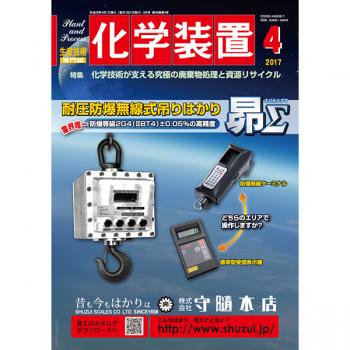化学装置 2017年4月号
【特 集】化学技術が支える究極の廃棄物処理と資源リサイクル
- 溶剤回収技術の新潮流―最近の技術動向―
- 綜研テクニックス 石川 諭
- SMCRを用いた多段抽出ユニットシステムとその適用例
- 神戸製鋼所 野一色 公二
- 究極の重質油分解装置(消費地精製の総仕上げ)
Ⅰ.石油を取り巻く環境(Ⅰ) - 化学工学会 SCE・ Netエネルギー研究会 原 晋一
【一本記事】
- 化学プラント設備における落雷事故回避と避雷針
- 落雷抑制システムズ 松本 敏男
- 高機能性シートおよびプリプレグ(複合材料)〔上〕
- 東京医科歯科大学 宮入 裕夫
- 「第6回高機能プラスチック」展/「第8回高機能フィルム技術展」の
見どころと「出展社リスト」 - 編 集 部
【特別寄稿】
- 広い電位窓を示すAI二次電池用電解液の開発と電池作製システム
- 大阪府立大学 知久 昌信、井上 博史
【新隔月連載】
- 変化する水処理市場と求められる技術・水処理エンジニアリング
企業の果たす役割(1) - AWBC 矢部 江一,上海交通大学 張 振家
□巻 頭 言□
- プラント事故に想う
- 化学工学会 安全研究会 澁谷 徹
- 情報ファイル「ジャパン・テクノロジー・サミット」で最新技術を紹介
- ハネウエル社
○技術トピックス○
- 波動式ふるい分け機「ジャンピングスクリーン」
- ユーラステクノ
【新短期連載】
- BCP/ BCMを考慮して Industry IoT対応の ISA 85に
ISA 99 を導入(第1話) - ICS研究所 村上 正志
【Column】
- 世界経済の大転換〔上〕
- モリエイ 内田 盛也
【連 載】
- プラントエンジニアリング・メモ(114)
- エプシロン 南 一郎
- 粉体の計量とその精度の実践的解説(4)
- フルード工業 小波 盛佳
- 安全談話室(127)
- 化学工学会SCE・Net安全研究会
- 地球環境とバイオリアクター(29)
- 近畿大学 鈴木 高広
- 技術者のための創造力開発講座(34)
- 飯田教育総合研究所 飯田 清人
- 知っておきたい微粒子をめぐる世界(43)
- 種谷技術士事務所 種谷 真一
□新化学化時代□
- “葉緑素”由来のα-アミノ酸合成の熟考
- 華和商事 村田逞詮,王 伝海
情報ファイル,催物案内,P&P Info.,コラム,次号予告。
【見どころ】
『究極の重質油分解装置(消費地精製の総仕上げ)』を化学工学会SCE・Netエネルギー研究会の原晋一氏より御寄稿を頂いた。
氏曰く、「石油エネルギーは、気候変動の問題もあり、世界的にはその伸びの抑制が叫ばれているが、エネルギーとしての利便性や価格から今後30年はエネルギーの主役であると予想されている。我が国においては人口減少による需要の減少が大きく、石油産業規模の縮小が避けられず、企業の統合や連携が進められている。」と指摘する。
続けて、「この統合・連携により、生産効率の悪い製油所は生産停止となると考えられるが、その先、今後考えられる船舶燃料の低硫黄化や、電気自動車の普及等にそる製品構成の変化、さらには地政学的要因による原油ソースの不安定化や温暖化問題から、装置産業である石油精製においては装置構成を大きく変えて対応する必要であると考えられる。」「そのためには、石油資源量が多くかつ中東地域以外の地域に賦存している超重質原油の処理可能化や、需要がほぼ無くなる重油生産の停止や、質的に需要の持続性が続くと考えられる中間留分石油製品の生産への特化が必要である。その方法は、原油中にある重質残渣油、特に減圧残渣油を、分解する能力を拡大することだが、現在進んでいる企業の統合・連携により原油処理装置の停止、引いては減圧残渣油分解能力の上昇が行われる事は期待されている一つの動きである。ただ、さらに将来必要と考えられる燃料重油生産の完全停止化や、原油ソースの重質化に対しては、原油の重質化もあり不十分で、中間留分を多く生産でき、かつ超重質原油を含む重質油を完全分解できる重質油分解装置の新設、その中でも原油中の最重質留分である減圧残渣油をほぼ完全に分解できるスラリー床水素化分解装置の新設が、効果的である。その時、投資効果を大きくするには、現在進んでいる統合・連携の動きをさらに進め、装置産業の特性を生かすべく、各製油所・企業が共同で大規模な重質油分解装置を建設・運営することが効果的である。このことにより、原油がほとんど無い我が国が石油産業の基本方針として設定してきた、消費地精製主義の総仕上げが行われると考えられる。」と。
今回、石油産業の統合・連携の生産サイドから見た意味と、その動きを受け継ぎ、今後さらに必要とされる生産効率化のあり方を“石油精製技術”の面から、経済性を含め、5月号以降、計3回に渉って解説して頂くこととなった。
※ 定期購読お申し込み後の購読契約は自動継続となります。
※ 海外からのご注文は別途、為替手数料がかかります。
FAX送信にてお申し込みをされる方はこちらのPDFファイルを印刷してご利用ください。
※Adobeアクロバットリーダーがインストールされている必要があります。
※クレジット決済ご希望の方は
こちら(富士山マガジンサービス)よりお申込み下さい。
(但し、国内ご契約のみとなります。)
1部:1,848円 (税込)※別途送料200円
定期購読一年:22,176円 (税・送料込み)
| ITEM NAME | 化学装置 2017年4月号 |
|---|---|
| ITEM CODE | PAP201704-f~PAP201704-m |
| PRICE | 1,848~22,176 円(税込) |